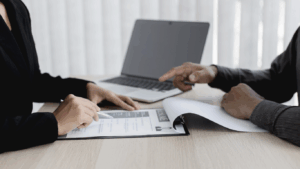人事評価制度の運用で業績改善や人材育成を実現するには?
人事評価制度を導入したけれど、運用がうまくいっていないという話はよく聞きます。むしろ、大半の企業が自社の人事評価制度の運用に満足していないのが実情ではないでしょうか。うまくいっていないということは、何らかの課題を解決したいと考えて、人事評価制度を導入したが、導入後もその課題を解決できていないということです。
人事評価制度は運用こそが大事だとよく言われています。運用8割と言われたりします。このような状況もあり、人事制度の運用を支援するサービスも色々と提供されています。古くからあるものでは評価者研修があり、評価会議や目標設定会議の支援、目標管理シートや人事評価シートのクラウド化、目標管理シートの添削サービスなどが登場しています。
色々と登場している人事評価制度の運用支援サービスですが、これらの導入により改善する可能性がある課題は、 ”人事評価の納得度を高めること” に限定されます。評価者研修や評価会議支援を通じて、妥当な目標設定のイメージを持ち、能力評価の評価項目の理解を深め、評価尺度(評語や評点)のレベル感について、評価者全員での評価目線を揃えていくことは、実現可能性が高まります。また、自社で求める内容のフィードバック面談を実施していくことについても実現可能性が高まります。
ところで、人事評価制度を導入することで実現したいことは、評価者の目線を揃えること、フィードバック面談の内容を充実させること、だったのでしょうか? それらの内容は、出来ていて当たり前であり、そこからの何らかの先の取り組みにより、人材の士気を高め、人材の成長を促し、ひいては会社の業績を向上させることが、人事評価制度を導入した目的だったのではないでしょうか?
そうであれば、評価者の目線を揃えること、フィードバック面談の内容を充実させること、という取り組みのもっと先に、人材の成長や業績の向上につながっていく、何らかの取り組みが必要となってくるはずです。
例えば、人事評価の結果を踏まえて、評価結果の内容と連動させて、部下の担当業務の難易度や業務量、範囲を検討して変更しているでしょうか? 同じ仕事を担当させる場合であっても、部下の裁量を変化させているでしょうか?
人材が成長するのは、人事評価の面談やフィードバックによるものではなく、仕事における試行錯誤を通じて成長するものです。人事評価の運用により人材を成長させていくには、きちんとした人事評価の結果であるなあらば、その内容を踏まえて、明日からの仕事への取り組ませ方を変える必要があるのではないでしょうか。そして、そのような取り組みを現場の管理職任せにするのではなく、人事評価制度の運用の仕組みとして強制的に組み込む必要があります。
また、他の例として、一定期間、低評価が続いた従業員が存在する場合、その部下の育成を現場の上司の責任にして放置していないでしょうか。人には向き不向きや好き嫌いがあり、それは仕事にもあるものです。ある部署で全くうだつの上がらない人材が、別の部署に移動させた途端に化けることもよく起こっています。低評価が継続している人材がいるのであれば、仕事の適性や上司との相性を踏まえて配置転換し、その後の成長を検証していく取り組みが、人を活かす人事、人的資本経営を目指すのであれば、必要となるはずです。
他にも、一定期間、良い評価が継続している人材がいる場合、もしかしたら本人にとっては簡単な仕事となっており、成長を阻害している可能性もあります。現場の上司としては手放したくない人材でしょうが、会社と本人の将来を考えると、もっと挑戦的で修羅場的な仕事に挑戦させる必要があるかもしれません。
人事評価制度の運用における不満、人事評価制度を導入した当初の目的から考えると、人事評価制度の運用支援として実施されている内容は、部分的な取り組みに終始している印象です。他にもっと取り組む必要のある、優先度の高い課題もあることがあまり議論されていない印象です。