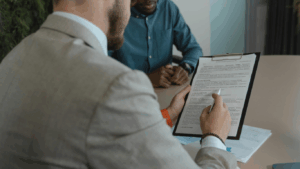ゆがめられた目標管理を超えて ~ 経営計画とつながる目標管理(MBO)へ ~
日本において、目標管理(MBO)は「ドラッカーが提唱した」として広く導入されてきました。そしてその際、「部下が自ら目標を設定し、それを自己管理させることが重要である」という説明がなされ、「上司が部下の目標設定を指示することはNG」「部下が好きに目標を設定して自己管理させることが本来の姿」という主張も少なくありません。しかし、実際にピーター・ドラッカーの著書「現代の経営(1954)」を読み解くと、こうした解釈には大きな誤解があると感じざるを得ません。
目標管理という概念を組織運営に持ち込んだドラッカーが繰り返し述べているのは、目標とは組織の成果を上げるために、経営計画と連動し、全社一体で取り組むべきものであるということです。
『現代の経営』の第11章「自己管理による目標管理」において、ドラッカーは次のように述べています。「事業が成果をあげるには、1つひとつの仕事を事業全体の目標に向けなければならない。仕事は全体の成功に焦点を合わせなければならない。期待すべき成果は事業の目標に基づいて決められる。それは組織の成功に対する貢献によって評価される。組織に働くものは、事業の目標が自らに求めているものを知り、理解しなければならない。上司もまた、彼らに求め期待すべき貢献を知らなければならない。そして、彼らを評価しなければならない。」期待すべき成果=”目標”は、事業の目標に基づいて決められる、と書かれています。この言葉は、目標設定がトップダウンの構造であることを明確に示しています。経営者が策定した経営計画が起点となり、それを各部門や各担当者の職務に応じて目標として細分化していくという構造こそ、ドラッカーが目指した目標管理の姿なのです。
しかし、ドラッカーは次のようにも述べています。「マネジメントたる者は、自らが率いる部門の目標は自ら設定しなければならない。上司(部門長の上司)は、そのようにして設定された目標を承認する権限を持つ。だが、目標の設定はあくまでも部門長(部下)の責任であり、しかも最も重要な責任である。」この文章だけを切り取ると、「上司が部下の目標を設定・指示することはNG」「部下が好きに目標を設定して自己管理することが本来の姿」とも解釈はできます。
ただし、続きがあります。「目標は好みではなく、組織の客観的なニーズによって設定しなければならない。まさにそれゆえに、誰もが自らの属する上位部門の目標の設定について積極的に参画しなければならない。(中略)上位の部門の目標設定に参画して初めて、彼らの上司も”彼らに何を期待し、どれだけの厳しい要求を課すことができるか”を知ることができる。」最終的に目標として設定することを決めるのは本人であるが、その目標の内容は、好き勝手で良いわけではなく、組織の客観的なニーズ=事業目標に基づいて決められるものであり、そのために上司は厳しい要求も課していく、と説明しています。
これに対し、日本における目標管理では、「部下が自ら好きに目標を設定し、その達成度で評価される」という制度にすり替えられているケースを多く目にします。そして人事評価における業績評価ツールとして利用されています。この運用は、本来の趣旨から大きく逸脱していると言わざるを得ません。その結果、社員は人事評価を意識しすぎるあまり、防衛的な行動に出るようになります。つまり、「確実に達成できそうな」低い目標を設定することで、自身の評価を守ろうとするのです。こうした行動は、組織全体のチャレンジ精神や創造性を削ぐことにつながり、本来の目標管理が果たすべき役割――すなわち、組織全体で成果を最大化すること――を妨げる要因となっています。
さらに、上記のような誤解に基づいた目標管理を運用すると、目標そのものが経営計画から乖離しやすくなります。部下が自分の理解や都合だけで目標を設定する場合、企業全体の戦略や方針との整合性が損なわれる可能性が高くなります。上司もまた、その目標を補助的にレビューするだけにとどまり(上司が部下の目標を設定・指示することはNGなので)、経営層の意図と現場の動きとの間にギャップが生じやすくなります。
このような形で歪められた目標管理について、かつて一倉定氏が「ゆがめられた目標管理」という著書の中で警鐘を鳴らしています。一倉氏は、目標管理を経営管理の中核としながらも、それを上司が部下の目標を設定・指示することはNGで、部下が好きに目標を設定して自己管理させる ”ゆがめられた目標管理” によって個人評価のツールに貶めることの危険性を明確に指摘しました。この視点こそ、現在の日本企業が再認識すべき重要な論点であるといえるでしょう。
このような誤解を招いている一因として、「現代の経営」の翻訳にも大きな原因があると考えています。翻訳では、「Management by Objectives and Self Control」を「自己管理による目標管理」と訳しています。この翻訳は誤解を招く内容になっていると私は考えています。正しくは、「目標と自律によるマネジメント」ではないでしょうか。噛み砕くと、目標(Objectives)と(and)自律(Self Control=自身に求められる役割を踏まえた主体的な自己管理)による(by)成果創出に向けた活動管理(Management )、という内容が、ドラッカーの文脈を踏まえた正しい訳ではないでしょうか。
日本で散見される「部下が自ら好きに目標を設定し、その達成度で評価される」という目標管理の運用は、ドラッカーが『現代の経営』で提唱した本来の目標管理とは大きくかけ離れたものです。この誤解を正し、目標管理を人事評価のツールとしてのみの運用ではなく、経営管理の中核に据え直して運用していくことが重要です。
企業が目標管理制度を再設計する際には、まず経営計画を明確にし、その意図と方向性を現場に具体的に展開することが不可欠です。そして、各部門・各個人がその意図に沿って役割と責任を理解した上で、上司からの要望や要求をベースに上司と部下で協議し、最終的には部下が自らの業務目標を設定=決定し、日々の活動に反映させていく。このプロセスを通じて目標管理は、はじめて組織全体の成果を導く有効なツールとなり得るのです。
※出所 現代の経営(上) ピータードラッカー著 上田惇生訳 ダイヤモンド社 2006年