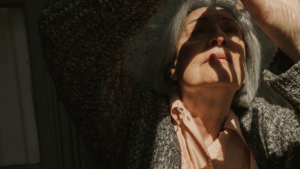抽象的な能力評価の問題点と有効な対応策
多くの企業が人事評価において能力評価を採用しています。しかしながら、現状の能力評価には「抽象的すぎる」という根深い課題が存在します。評価項目が曖昧であったり、評価者の主観に左右されたりすることで、評価の公平性や納得性、さらには育成効果にも大きな影響を及ぼしています。
日本企業の能力評価でよく見られるのが、「コミュニケーション力」「リーダーシップ」「柔軟性」といった抽象的な評価項目です。これらは組織が求める人材像や理想像を表すものとして一定の意味はありますが、評価基準としては非常に曖昧です。そのため、具体的に何をどう評価するかが評価者によって大きく異なりがちです。たとえば「コミュニケーション力」という言葉ひとつを取っても、「積極的に発言すること」「相手の話をよく聞くこと」「適切に報連相を行うこと」など、解釈の幅は非常に広くなります。
さらに、こうした抽象的な項目は、評価面談の際に具体的なフィードバックを与えにくいという課題もあります。被評価者は「自分の実務においてどの行動を改善すればよいのか」が見えづらく、成長に向けた明確な行動課題をつかめないことも少なくありません。具体的にどのような場面で何を変えればよいのかが不明確なため、効果的な成長につながらないケースも多く見られます。
このように、抽象的な能力評価は、評価の納得性を著しく損なうだけでなく、人材育成の実効性をも低下させる「負のスパイラル」に陥りやすいのです。曖昧な評価項目は具体的な判断基準がないため、評価者の負担も大きくなり、結果として評価業務自体が疲弊してしまいます。
加えて、抽象的な能力評価は、組織の経営戦略や具体的な職務内容と連動していないケースも少なくありません。人事評価とはこういうものだという慣習から能力評価の形式と項目が採用されています。そのため、経営が求める価値創造や成果に直結しているのかがよくわからない評価項目も多く含まれ、個人の評価と組織の目標との間に乖離が生じ、組織全体としての一体感が損なわれるリスクもあります。
こうしたなか、評価の精度向上を目的に導入された手法の一つが「コンピテンシー評価」です。コンピテンシー評価は、特定職務における高業績者の行動特性を抽出し、それを評価項目として体系化することで、評価の具体性と再現性を高めようとするものです。理論上は、能力を具体的な行動に落とし込むことで評価の曖昧さを減らすことが期待されています。
しかし、実際には多くの企業においてコンピテンシー評価は従来の能力評価と大差なく、評価項目も抽象的な表現に留まってしまっているのが実情です。結果として、表現こそ変わっていても、評価の主観性や納得性の低さといった根本的な課題は解消されていないケースが散見されます。
こうした課題に対する実務的かつ有効な対応策として、近年注目されているのが評価基準として実務の実態に即して評価項目を設計する方法です。各職種&役職に求められる「重要成果」「重要業務」「重要知識・スキル」を明確に定義して、評価していく方法です。
最大の特長は、「何をすれば評価されるのか」が明確かつ具体的である点です。評価基準を成果(アウトプット)、業務プロセス(プロセス)、必要な知識・スキル(インプット)に分解することで、評価者は日々の実務に基づいて評価でき、被評価者も自らの評価ポイントを把握しやすくなります。
また、評価基準に必要なスキルや知識が明示されているため、評価結果をもとにした育成計画の策定も容易です。被評価者は自身がどのスキルを強化すべきかが把握しやすくなり、組織としても育成方針を明確に描くことができます。
さらに、各職種ごとに実務に基づいた評価基準を設計することで、経営戦略上重視される成果や行動に評価の焦点をあてることが可能となり、評価制度と組織目標(経営計画)の整合性も向上します。これにより、組織全体の目標達成力も高まっていくのです。
もちろん、こうした評価制度の導入にあたっては、各職種&役職に求められる「重要成果」「重要業務」「重要知識・スキル」を設定する精度の向上、現場との合意形成、実務の変化に対応した柔軟な見直し体制の構築など、制度設計と運用において一定の準備と継続的な改善が求められます。
まとめ
抽象的な能力評価は、その曖昧さと主観性により、評価の公平性や納得性を損ね、育成や経営戦略との連携も困難にしています。コンピテンシー評価も一定の意義はあるものの、実務に落としきれないまま形骸化しているケースが多く、解決には至っていません。
これに対して、実務に基づいて「何をどう行い、どのような成果を出すべきか」を明確に定める評価方法は、実務との整合性が高く、育成と経営をつなぐ有力な評価手法です。現実的な選択肢といえるでしょう。